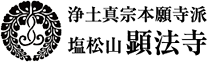兵戈無用(ひょうがむよう)
『仏説無量寿経』というお経には、「兵戈無用(ひょうがむよう)」という言葉が出てきます。武力も武器も用いる必要が無いという意味の言葉です。この言葉が出てくる一節は、「仏が歩み行かれるところは、国も町も村も、その教えに導かれないところはない。そのため世の中は平和に治まり、太陽も月も明るく輝き、風もほどよく吹き、雨もよいときに降り、災害や疫病(えきびょう)なども起こらず、国は豊かになり、民衆は平穏に暮らし、武器をとって争うこともなくなる。人々は徳を尊び、思いやりの心を持ち、あつく礼儀を重んじ、互いに譲(ゆず)り合うのである。」というところです。
仏法がきちんと伝わり、国も豊かで災害も起こらないようになる、そんな理想的な社会でこそ「兵戈無用」というのは、実現することだということでしょうか。そうだとすると、異常気象、凶悪な事件の続発、絶えない戦争と平穏な暮らしとはどんどんかけ離れていくような社会で「兵戈無用」が実現できるはずはないと考えてしまいます。しかし、私自身がまず仏法を聞き、心穏やかに過ごし、暴力を用いず平和でありたいと願う生き方をしていく心が一人一人に浸透していけば、この言葉に表される理想も少しずつ実現されていくのではないでしょうか。
昨年は、戦後70年で様々な角度から「戦争」「平和」をとらえる試みがされてきました。今回、ホームページを立ち上げるにあたり、人々の中から失われつつある「戦争の記憶」をなんとか留めることができないかを考えました。そして、門徒さんの「戦争の記憶」を集め、「兵戈無用」や「平和」、「命」について考えるきっかけとしたいと思います。争いが絶えない世界だからこそ、「兵戈無用」の本当の平和を願う国であって欲しい、私は強く願ってやみません。
以下の文章は、門徒Sさんの体験記録です。Sさんは、戦後福島県の小学校教諭、管理職として児童の教育に携わってきました。そのSさんの昭和18年から昭和20年までの師範学校生時代の記録です。今後、門徒さんの記録や戦争に関わる物の写真などを増やしていく予定です。
「学窓からの決死の出陣」
昭和18年4月入学の樺太師範5期生男子部は、師範生として特異な運命をたどった。本課3年生在学中に陸海軍に入隊する者が大半を占め、昭和20年同級生はそれぞれ離散し、樺太での卒業生は約30名であり、多くは終戦後、全国各師範学校に転入、卒業となった。
戦局が急迫した昭和18年以降は、学校制度も次々と改革が行われた。昭和18年10月の全国学徒出陣が行われ、同年12月「徴兵特例臨時特例」によって、徴兵検査年齢引き下げが実施されることになった。これは、師範生も例外ではなかった。
昭和19年5月、樺太の豊原第一国民学校だったと思うが、その講堂で徴兵検査を受けた。身体検査(ハンカチ型ふんどし姿)、簡単な試問、身体検査があり、最後に徴兵官から「○種合格、陸軍○○兵」などと判定を宣告された。このころは、通年動員制のもとで勤労動員と教練・修練が毎日であった。修学旅行にかえて、秋頃、部隊で数日間軍事講習に参加した。9月卒業の先輩は、多数が陸軍予備仕官や海軍予備学生となり教壇立つことなく、戦場におもむいた。
昭和20年に入り戦況はますます緊迫し、軍の将校不足は深刻となり、幹部養成が急務となったらしく、「陸軍特別甲種幹部候補生」の制度が2年目となった。これは、高専以上の在学者を試験の上採用し、兵としての訓練期間を省略していきなり予備士官学校に伍長として入校させ、約1年半で予備少尉に任官させるという、かなり迅速な戦力化を図るものであった。
昭和20年、過酷な戦局のもと、学校から戦場へと直行せざるを得なくなっていった。本科2年の後期に、特甲幹募集があった。表向きは志願とはなっているが実質は受験命令である。「私は樺太の教育者たらんことを念願している学究の徒です。軍幹部など望まず、教育報国の至誠をまっとうしい。」とはとても言えない状況であり、受験せずとも部隊への入営令状は目前に迫っていた。
試験日は何日だったか定かではないが、健康検査と口頭試問だったと記憶している。
「合格するのが幸か不幸か?」
「何をもって優劣を判定するのか?」
図りかねるが、採用(軍)側の都合で決められたのである。軍人勅諭の一節を聞かれたが、すらすら大声で言えたから合格だったのかの感もした。後日連絡があり、「5月13日 13時 千葉県津田沼 東部軍教育隊に入校すべし」とあった。
昭和20年4月17日、出陣式の日が来た。講堂に全校生が出席。4月とはいえ北方のこと、寒気厳しい中、入学式直後に在学生の出陣という異例さに加えて、緊張感、悲壮感に満ちた雰囲気であった。上田校長の出陣壮行の辞があり、続いて紹介が行われた。各自、壮途に赴く者としての決意を言辞に短歌詠にそれぞれ披露した。
「国の大事に殉ずるは我等の本分ぞ」
「樺太師範での想い出のいろいろ」
「軍隊即戦場 まず生きては帰れまい」
「戦争が終わったら早く樺太に戻りたい」
等々、誰しもが頭中をよぎるのを禁じ得なかった。最後に全員で「海行かば」を歌った。何度もこの講堂で歌ってきたのだか、今こそこの歌詞の通り我々は出で発つのだ。出陣式であるとともに離校式であり、われわれ5期生の卒業式でもあり、事実上永久の決別を予測できる、誠に感慨無量の式であった。
ブログはじめます!
顕法寺のブログページです。
よろしくお願いします。
概要
| 名称 |
浄土真宗本願寺派 塩松山 顕法寺 |
| 住職 |
髙橋 融 |
| 所在地 |
〒964-0902 福島県二本松市竹田1-198 |
| TEL / FAX |
0243-22-1081 |
沿革
当山は、開基長察律師の創立です。本願寺第九世教恩院実如上人の代に得度し、特に直筆の御書を拝受し、大永二年(1522年)奥州塩松の郷に一寺を建立して、聞法衆生に努めました。その後、二本松市小浜新町に移りました。顕法寺の開基長察律師は、天文八年(1539年)に往生しました。
二世祐身、三世勝誓、四世伝栄、五世祐照、六世祐玄と法庭を拡げていきます。
七世土身は、二本松城主加藤民部大輔明利公の菩提寺として二本松城下池ノ入に移り、寺領五十石を毎年賜りました。その後、丹羽光重公が入国し町割の折、前城主の菩提寺故に明治に至るまで寺領十石を賜り、現在地(福島県二本松市竹田)に本堂を移転しました。
八世の休身の弟休山は、元禄年間に小浜跡寺を分割し法楽寺と改称しました。
九世正諦、十世順応、十一世宝雲、十二世宝順、十三世宝林と続き十四世西信の代の明治維新後、寺門の維持困難となり山林等を開墾しています。
明治六年(1873年)学制発布の折、竹根小学校創設に本堂を貸与して教育と社会奉仕に尽力しました。明治二十五年(1892年)4月25日竹田根崎の大火の折、本堂、庫裡、山門が全焼します。しかし、門信徒の必死の努力により御本尊をはじめ法宝物避難して無事でした。
檀頭七島徳太郎氏はじめ全門信徒の格段の報謝行により、十五世弘長代鋭意復興に尽力し、本堂、庫裡、山門、太子堂を再建し、十六世義弘代の昭和二年(1927年)に完成しています。
十六世義弘は、住職在位60年に及びました。十七世弘融代に本堂、庫裡に傷みが多くなってきたため、檀頭七島柏氏を中心として昭和六十二年(1987年)に本堂建設委員会を組織し建設にあたり、平成元年(1989年)に本堂、庫裡が完成しました。これが現在の本堂です。そして、平成二十五年(2015年)4月24日十八世顕融の継職法要を行いました。
史跡
(1)加藤明利公墓所
加藤明利は、慶長四年(1599年)伊予国松山(現・愛媛県松山市)に加藤嘉明の次男として生まれました。
その後、二代将軍徳川秀忠に仕え、扶持米千俵を給され、元和二年(1616年)に従五位下民部少輔に叙任されています。
父の嘉明は、賤ヶ岳の戦いに「七本槍」の一人として活躍した戦国武将です。後に伊予松山二十万石の城主となっています。松山城築城直後の寛永四年(1672年)二月、蒲生氏に代わって会津四十万石の領主として入部しました。入部直後の三月、嘉明は、女婿である松下重綱に二本松五万石を、明利公には三春三万石を支配させました。同年十月に重綱が亡くなったため、翌年一月にその子長綱を三春に移し、明利公には、二本松三万石を与えました。
明利公は、二本松城着任後すぐに、山の半ば以上を城郭として、本丸、一の丸、二の丸を整備しました。
さらにその山腹を切り開いて郭内と称し、重臣の屋敷を設けるなど、蒲生氏時代の城郭を拡張、改修しました。
明利公は、二本松城主として十三年の長期にわたり統治し、寛永十八年(1641年)三月二十五日に四十三歳をもって亡くなりました。
法名は「宝樹院殿雲心夢大禅定門」であり、当顕法寺に立派な位牌が安置されています。

加藤明利公墓所

加藤明利公墓所参道1

加藤明利公墓所参道2
(2)服部宇之吉博士顕彰碑
中国哲学の世界的権威者、服部宇之吉博士は、慶応三年(1867年)四月三十日に二本松藩士の服部藤八の三男として生まれました。母の病没、父の戊辰戦争戦死により、弟夫婦が服部宇之吉博士を養育しました。
明治二十三年(1890年)東京帝国大学哲学科を卒業し、明治三十二年に同大助教授となり、清国とドイツに留学しました。同三十五年同大教授に就任直後、清国政府の要請で北京大学主任教授となり、清国教育界発展に貢献しました。大正四年(1915年)米国ハーバード大学教授に就任しました。帰国後、東京帝国大学文学部長に就任し、同十年、東宮職御用掛を拝命しました。御講書始では、天皇陛下への漢書御進講の栄に再三浴しました。服部宇之吉博士は、中国の礼思想の理論的体系化に尽力したり戒石銘研究の基本「旧二本松藩戒石銘説明書」を詳述したりしました。昭和十四年(1939年)7月11日に七十二歳をもって亡くなりました。東京護国寺にお墓があります。顕法寺は、服部家の菩提寺になっています。

服部宇之吉博士顕彰碑

服部家墓所
(3)二本松少年隊 田中三治の墓
江戸時代から明治時代へと移り代わる時代の中で戊辰戦争が起こりました。二本松藩は、東軍に属しました。そして、薩摩・長州率いる西軍に徹底抗戦の構えを取ります。しかし、西軍は、近代的な戦力を持ち、奥州に攻め入ってきました。
奥州の諸藩は、奥羽列藩同盟を結び抵抗しましたが、西軍の戦力を前に同盟諸藩は次々に降伏してしまいます。
その中でも二本松藩は最後まで戦い抜く姿勢を崩しませんでした。そして、慶応四年(1868年)、藩の成人年齢を「十五歳」にまで引き下げました。これにより十五歳以上の男子が出陣することが認められました。二本松藩には昔から「入れ年」と呼ばれる習慣があり、年齢を二歳さばを読むことが黙認されていました。そのため、この時も入れ年で「十三歳」以上の男子が出陣を許可されることになったのです。こうして出陣した十三歳以上、十七歳以下の少年たちを「二本松少年隊」といいます。
田中三治は、田中昇蔵(奥書役)の弟です。樽井弥五左衛門隊に属し、慶応四年(1868年)七月二十七日、糠沢村(福島県本宮市糠沢)上ノ内の民家に宿陣しているところを薩摩藩軍に襲われて戦死しました。十六歳の短い命でした。顕法寺は、田中家の菩提寺になっています。

田中三治墓所